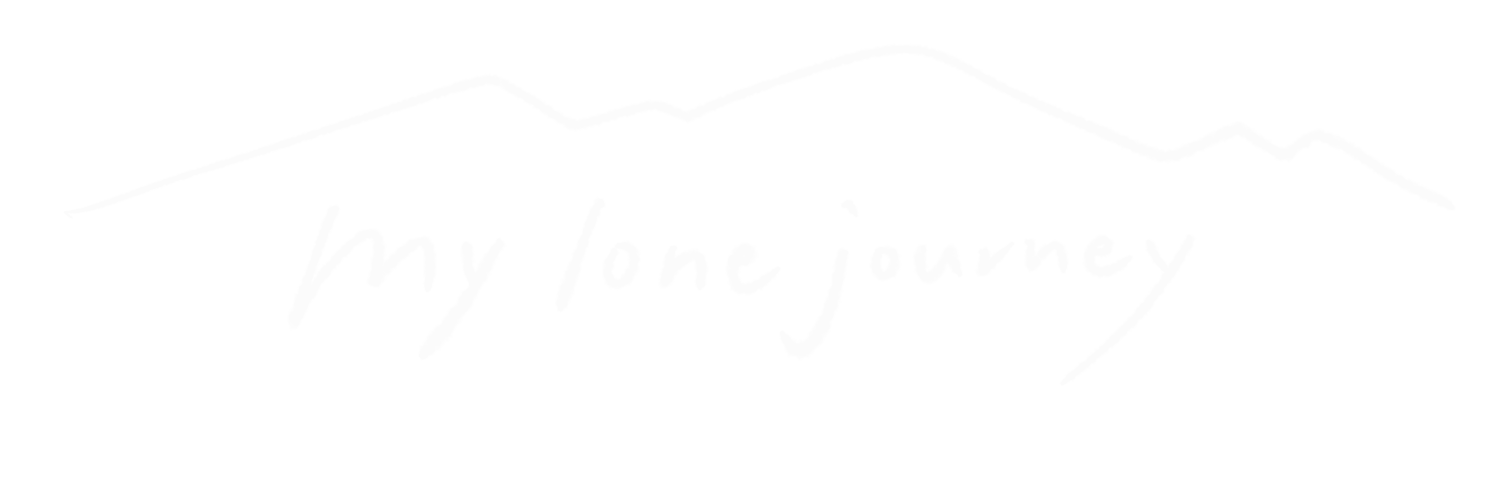AC.301年から続くアルメニア正教、世界最初のキリスト教布教国。古くからの修道院群はひっそりと、森の中にあることが多かった。


誰もいない教会、残り香だけが周囲に漂う。内部には石の隙間の小窓から差し込むわずかな光と蝋燭の灯りだけ。
○
トルコからジョージア・アルメニアと陸続きで渡った。国境、そこには確かに”線”があり、その先には全く異なる世界が広がる。その不思議さをどうにか理解したくて、必死に歴史を辿れば、やっぱりそこに宗教が存在する。アルメニアという輪郭を理解するのもまた、とても難しい。
アルメニア正教とジョージア正教、その両者を隔てるものを探ると、キリストの「神性」と「人性」について定めたカルケドン公会議(451年)にまで遡るようだ。カルケドン派は「二性説」・”イエスは人であり、神でもあるという両性を持つ”という考え。カトリックやプロテスタント、東方教会など多くのキリスト教ではこの考えを支持している。それに対し非カルケドン派は”イエスは神と人が交わった一つの存在である”という考えを持つ。ジョージア正教はカルケドン派の東方教会に属する宗派なのに対し、アルメニア正教は非カルケドン派のオリエンタル正教会に属する宗派。そもそも思想の交わる地域が異なる。つまり、アルメニア正教とジョージア正教が1500年以上、統合することなくそれぞれの立場を保ち続けているのは、そもそもの考え方が異なるからだ。考え方の違いが国境を成し、文化に、それぞれの人生のアイデンティティになっている。宗教的な背景が、その国の歴史・政治・文化に大きな影響を与えているのだなとこの旅で改めて感じることになった。でもその混沌の歴史を形成するのは、その土地々々の持つ風土そのものなんだと、ここ大陸にいると思う。


イスラム教へと改宗していったオスマントルコや、東方教会に属するジョージア正教・ロシア正教などの勢力を間近に、それでもアルメニア正教独自の祈りを守り続けるにはひっそりと、身を隠すしかなかったのかなと思う。


古代のアルメニア正教の修道院を巡ると、もっと土着的な祈りを感じる。初期のキリスト教はもっと土着的な祈りとの連続性の中にあったのだなと気付かされた。


この国の修道院群には、至る所に大小様々な十字が刻まれている。祈りというよりも、呪いという感じがする。
十字というシンボルそのものの意味を調べてみると、十字乃至、卍は、”完全”としての意味で認知され、キリスト教に限ることなく世界中に残っているよう。またその十字は多く、生命樹に見立てられるようだ。そのことを知ると、アルメニアであちらこちらで見かけるハチュカル(石碑)は、円球の大地に木がそびえているような表現に思える。キリスト教のシンボルでありながら、どこか自然への畏敬を感じさせる怖さがある。




キリストに祈りを捧げる修道院でありながら、既に自然へと還った修道院、宇宙を意味する十字がそこらじゅうにあしらわれ、自然信仰そのものに思えた。それでも神に人という性質を与えること(受肉)で、親近感を憶えるように、この不確かな世界で生きるためには、人としての言葉や人肌・体温が必要だったのかもしれない。この旅で、なぜ人は地球そのものに祈れないのかと疑問を持ちながらも通り着いた私なりの答えだった。
政治や権力、民族間のアイデンティティなどが対立する際に「正当化の道具」として利用されてしまう宗教。本来は生きるなかでの過ちや、悲しみを癒し、慰め、それでも生きてゆくための人の知恵だったはずなのに。
そもそも現代はなんで自分の信じるものを語ることをタブー視されるんだろう。それを信じているあなたが一番それの良さをわかっているはずなのだから、それのいいところを教えてくれよ…と、思う。宗教を語ることが、誰かとの対立を恐れることでなく純粋に、新鮮な考え方に出会ったりして温度を上げてくれるようなものであったら良いのに…